| 2011年2月号 | ←前へ 次へ→ | ||
 |
|||
| あなたはいかなる像も造ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にある、いかなるものの形も造ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。わたしは主、あなたの神。わたしは熱情の神である。 | |||
| 出エジプト記20章4節(新共同訳) | |||
| 「いかなる像も造ってはならない」―始めから偶像と分かっていて偶像を作る人はいないでしょう。拝む者も、やたらにひれ伏したり仕えたりはむしろしたくないです。ですから私たちは自分のことを、偶像を作ったり拝んだりはしないと思っています。だとするとこの第二の戒めはどんな意味があるのでしょうか。 世の中には、いかにもインチキくさい偶像も確かにあります。しかし実は真剣に拝んだり仕えたりする偶像があふれています。 第一の戒めのところで記しましたが、神様に従う道を進んでいる旧約の人々自身、偶像を作って拝んだり、身につけてお守りにしたりしています。私たちは不安や恐れややるせなさが広がると、神様以外のものを神様扱いし、それを偶像と思わないで頼る弱さがあります。溺れる者は藁をもつかむ心境になるのです。その心は、たとえ溺れなくても頼りにできるあるいは自分の益になる人や物があれば頼りにしたくなります。偶像、それは人間が自分のために作り出す神のことです。ですから偶像は必ずしもお人形のような格好をしてはいません。私たちは沢山の偶像を自分の周りに抱えています。 これは目に見え物や存在だけではありません。目に見えない偶像もあります。主なものを上げれば、権威、栄誉、繁栄、…、このたぐいです。これは本来神様の専売特許のはずです。ところが私たちはこれを神様のもとから自分の所に引き込んで、これを頼りに生きようとするようになっています。自分だけの権威、也栄誉などは自分を神様にしてゆく作業です。偶像化を進めるのです。 実は、社会の底辺に暮らす人が、人の権威や、栄誉など「そんなもの屁でもない」と言い切る自由さ持っていることを知ることがあります。その人々には挫折、あきらめ、敗北感が混じっているかもしれません。でも権威、栄誉の類、そんなもの人間になくても生きることができると教えています。真の権威、真の栄誉は神様のもとにしかありません。私たちはいたるところで神ならぬものを神にする天才である気がしてきます。この第二戒、まず自分が聞く耳を開く者でありたいです。 聖書の語りかけを聞き、自らを低くして、私たちの造り主であり、全能なる唯一なる神様にこそ、謙遜な思いを重ねて、ひれ伏して、偶像を持たない作らない大切さ、を知ってゆきたいです。 ( 牧師 金井俊宏 ) |
|||
 |
|||
|
■安田 志峰 |
|||


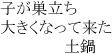 
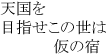
|
|||
|
トップページへ | |||
|
|
|||