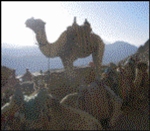| 2010年5月号 | ←前へ 次へ→ | ||||||||
 |
|||||||||
| 翌日、また出て行くと、今度はヘブライ人どうしが二人でけんかをしていた。モーセが、「どうして自分の仲間を殴るのか」と悪い方をたしなめると、「誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか。お前はあのエジプト人を殺したように、このわたしを殺すつもりか」と言い返したので、モーセは恐れ、さてはあの事が知れたのかと思った。ファラオはこの事を聞き、モーセを殺そうと尋ね求めたが、モーセはファラオの手を逃れてミディアン地方にたどりつき、とある井戸の傍らに腰を下ろした。 | |||||||||
| 出エジプト1章22節 2章11節~(新共同訳) | |||||||||
| モーセが成人したころの話が記されています。若気の至りでしょうか、それとも自分の正義感に燃えてでしょうか、彼はエジプト人が我がヘブライ人(ユダヤ人のこと)を打つのを見たものですから、そのエジプト人を撃ち殺して砂に埋めてしまうのです。もちろん誰も見ていないのを確かめてです。 前回記しましたがモーセは、ユダヤ人の子として生まれナイル川に捨てられるはずが、エジプト王女の子供として生き延びることとなり、でも乳母として育ててくれたのは実の母でした。そんな境遇がモーセに何を与えたか、思い計るしかありませんが、乳母(母)から聞いたのでしょうユダヤ人としての意識はしっかり持っていたようです。 エジプト人を殺した翌日、モーセはユダヤ人同士がけんかをしているのを見かけます。悪い方の者を「どうして自分の仲間を殴るのか」と叱りつけると、その男はモーセがエジプト人を殺したのを見ていたのでした「同じように俺を殺す気か」と食ってかかってきました。 この時モーセはとっさに、仲裁どころではない事態になることを悟ります。死刑になるのは間違いないことを、です。 即座に、遠い遠い地でミディアンに逃れます。そこでが安住の地になります。祭司の家族に受け入れられ、その娘の一人チィポラと結婚し、子供も与えられます。モーセにとっては生涯で最ものびのびとゆったりとできた時期であったろうと思います。 他方エジプトには、多くのユダヤの人々がいます。王の締め付けは厳しくなり、激しい労働を強いられ、嘆きの声が上がり、行きどころのない様相になるのです。しかし時が過ぎてゆきます。その王も死を迎えます。ということは、モーセは彼らのいるエジプトに再び戻ることが可能になったということです。 聖書、ここまではモーセの神様による歩みの準備期間です。私たちは神のご計画がどこにあるかを定かにできませんが、出エジプト記1,2章は、なぜか神様がご計画をもってモーセに関わっておられて、その数奇な人生が与えられていると感じ入ります。 王から逃げても、神から逃げてはいないモーセを思います。 ( 牧師 金井俊宏 ) |
|||||||||
 |
|||||||||
| ■小栗 和子
聖地旅行報告シリーズ 4-1 以前、聖地旅行が紹介されたのは、半田教会の篠田牧師が行かれるときだったように思う。この時は、1週間以上も勤務を休めないため、行くことができなかった。豊田教会でも中西牧師のとき、計画があったが、実現に至らなかった。しかし、やっとその時が来た。2009年神様が旅行に参加できる機会を与えてくださった。ハレルヤ!イスラエル聖地旅行。 しかしこの3年間、健康がすぐれず体力の無さを思うと、11日間の長旅、ご迷惑をかけずに行って来ることができるかと、不安がよぎった。が、体調も少しずつ回復しており、与えられた時を大切に思った。 そんな思いで参加したので、聖書にあるモーゼの登ったシナイ山に登れたことやイエス様誕生の地、歩まれた地に立てたことの喜びは、感激で、まさに感謝!感謝! ―思い出をふりかえるとー 中部空港を出発して、14時間余、飛行機に乗り、エジプトのカイロに着く。空港のトイレにはがっかり!日本では当たり前に使っている「水」の大切さを知らされた。バスで走ると休憩地は有料トイレ。もちろん、飲み水は、ガソリンより高い。やはり、砂漠、荒野を目の当たりにして、尊い尊い命の水なのだということを強く思わされた。 シナイ山: 真暗闇の中、崖っぷちの様な道であることに気づかず、2時間ラクダに乗って山小屋まで。夜空には星が煌いていた。石段800段を息を切らして、共に声をかけながら登る。
山頂には各国から来た大勢の人々で溢れていた。見晴らしの良い風の少ない場所を確保。気温は下がり、風も吹いて寒いが、重ね着とカイロで防寒対策は功を奏した。夜明け、コーランが響いてきた。いつ日の出があるのかと徐々に白んでくる山の端に注目した。シナイ山のご来光、陽を受けて回りの山々が刻々と変る様も壮大。下山中、すばらしい空の蒼に感動。一行のなかで一番若い杉浦姉妹の失われた靴事件は、途中の山小屋で、解決ができていた。靴が戻ったのだ。あの暗闇、あの広い場所でどのようにして捜し得たのだろうか。奇跡のように思えた。現地の人は厳しい環境にあって、一人では生きられない。それ故、団結、結束して、生きる術が磨かれているから、為し得た事なのだろうか。モーゼが「十戒」をいただいた地にあって、姉妹は恐怖悲惨の試練を与えられたけれど、主の導きのように、この旅で逞しい成長の恵みを受けられたと思う。  ガリラヤ湖畔: 山上の垂訓教会(1936年イタリアのムッソリーニの資金提供を受けて建てられたそうだ。)フランシスコ修道女による静寂を重んじた環境で管理されていた。 ガリラヤ湖畔: 山上の垂訓教会(1936年イタリアのムッソリーニの資金提供を受けて建てられたそうだ。)フランシスコ修道女による静寂を重んじた環境で管理されていた。八角形の建物は、次の八福を ①心の貧しい人々 ②悲しむ人々 ③柔和な人々 ④義に飢え渇く人々 ⑤憐れみ深い人々 ⑥心の清い人々 ⑦平和を実現する人々 ⑧義のために迫害される人々(マタイ5-3~10) (次号に続く) |
|||||||||
| ■深津 玲実 | |||||||||
 「水で手を洗うピラト」 「水で手を洗うピラト」マタイ27:24~25 *ユダヤは当時ローマの属国であり、ピラトはローマから遣わされたユダヤの総督であった。それ故、騒ぎを起こされては自分の失政になる。しかも、ピラトの妻から「夢をみたのでイエスと関わらないように」との伝言があった。イエスに罪を認めなかったピラトは何とかイエスを釈放したいと、重罪人のバラバを引き出し、当時のしきたりを用いて、どちらを釈放してほしいかと民衆に問う。が、ピラトの意に反して、民衆は、バラバを釈放しイエスを十字架にと叫ぶ。(この時釈放されたバラバを主人公にした小説が、スウェーデンの作家ラーゲルクヴィストの1951年度ノーベル文学賞受賞作品) *ここにいたってピラトは「この人の血について、わたしには責任がない。お前たちの問題だ」と言い、水で手を洗った。民はこぞって、「その血の責任は、我々と子孫にある。」と答えた。このことが、後々、ユダヤ人排斥の根拠になったと。 |
|||||||||
| ■安田 志峰 |
|||||||||

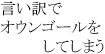
 

|
|||||||||
|
トップページへ | |||||||||
|
|
|||||||||