| 2010年4月号 | ←前へ 次へ→ | ||
 |
|||
| ファラオは全国民に命じた。「生まれた男の子は、一人残らずナイル川にほうり込め。女の子は皆、生かしておけ。・・・ 王女が、「この子を連れて行って、わたしに代わって乳を飲ませておやり。」と言ったので、母親はその子を引き取って乳を飲ませ、その子が大きくなると、王女のもとへ連れて行った。その子はこうして、王女の子となった。 | |||
| 出エジプト1章22節 2章9,10節(新共同訳) | |||
| 旧約聖書を読み進んでいます。今回から出エジプト記に入ります。この書の中心人物はなんといってモーセです。映画の「十戒」などご覧になった方も多いのでしょう。紅海の水が二つに分かれて、イスラエルの民を引き連れてシナイ半島へと渡った中心人物です。
生まれは、エジプトです。当時モーセが属しているヘブライ人は人の好まない重労働や汚れる仕事をして生きていました。それでも彼らの勢いは増しました。ある時警戒し始めたエジプト王は「男の赤ちゃんが生まれたら、みな殺すべし」というお達しを出します。主イエスの時代にもヘロデ王が2歳以下の男の子を皆殺しせよと命令を出したとあります。現代人の人権感覚からは計ることのできない権力者構造があり、それが通用したのでしょう。 さてモーセが生まれました。母親は男の子であることをどのように思ったでしょうか。数か月隠しながら育てますが、いずれは分かってしまいます。しかたなく防水を施した籠にこの赤ちゃんを入れ、ナイル川の芦の茂みに置いて、わが子の人生にかすかな望みをつなぎます。 そこへエジプト王ファラオの王女が水浴びに来て、赤ちゃんに気づきます。事をのみこみます。不憫に思い、育てることにします。王が殺せという、その赤ちゃんを王女は自分の子供にするのです。私たちは自分たちの打算や利得や権力で生きようとする一方で、このような慈しみを出す心もあります。それでも王と王女と真逆です。モーセはこうして命を落とさずに成長が与えられます。しかもエジプトの王女のまなざしのもとです。芦の茂みの奥で様子を見守っていたモーセの母親は乳母としてではありますが、赤ちゃんを育てることもできるのです。 私たちはこの先、モーセのその後の生きざまを見てゆきます。神様に心を向けて人々を導くその様を,です。厳しい局面を迎えること多くあります。それでも民のリーダーとして神様による歩みをそれてゆくことはありません。それを思う時に、エジプトの王女に見いだされたことも、ここに神様の配剤があると思わずにはいれられません。 神の勇者モーセが誕生しました。 ( 牧師 金井俊宏 ) |
|||
 |
|||
| ■(特別寄稿)久保地 順子
「49才で天に召された四日姉」 3月3日、10時半、タクシーを降りると、緑の屋根の鐘楼のテッペンに十字架が銀色に輝き、隣接するレンガ色の建物に「沼津教会」と大きく文字が浮かんでいます。 広い舗道を入り、二階の礼拝堂はほぼ満席。祭壇は白のストック、トルコききょう、マーガレット、かすみ草であふれ、その中に、ほんの少しうすいピンクが未だ若い四日さんにピッタリでした。その前に温和で小顔の彼女の遺影がほほえんでいました。200人は入れそうな会堂は、天井は木組み、壁はコンクリート打ちっぱなしと木の組み合わせ、窓は高く、ここにステンドグラスが入っていたなら欧米の教会にちかく、比較的新しい会堂だと感じました。 素朴な鐘の音が時を告げ、葬儀がはじまりました。牧師は何と大畠先生の時と同じ宮本牧師でした。(後で恵美さんに聞いたところでは、彼は沼津教会の牧師で大畠先生と同期生で55才と)聖書はコリント人への手紙13章8〜13。お説教は四日姉の受洗20周年の教会誌に寄せた原稿、夫淳一氏の話、大畠牧師と四日姉、宮田牧師3人の不思議な出会い等に沿って語られました。四日姉が豊田で教会に行けなくなったくだりでは、牧師の側から「大畠牧師がひとりで十字架を背負った」と語り心が痛みました。実は私自身も一年教会に行けず、日曜の朝は引きこもってました。牧師にとっても信徒にとっても「主よいずこに」と、途方にくれ試練の時だったと思い返しました。 又、四日夫妻は子供が与えられなかった分、裾野に行っても社宅で習字教室を通して多くの子ども達を愛しはぐくみ、その母親たちとも深い交流があったそうで、参列者の中は成長した青年たち母親たちであふれていました。聖書の「いつまでも残るものは愛」を実践した四日姉の49才の生涯が心に焼きつきました。 一ヶ月前に逢ったばかりの恵美さん、潤君、小泉姉、そして北田姉と中谷姉二人は成長した息子さんと一緒、そして野田姉と私、皆で献花し地上でのお別れをしました。 *聖地旅行シリーズは次号から掲載を続けます |
|||
| ■深津 玲実 | |||
 「死刑の判決」 「死刑の判決」マタイ27:15〜23 死刑の判決、死刑の執行、冤罪といったニュースが続いている。イエス様の死刑判決は明らかに冤罪で、しかも即執行された。 当時ユダヤ人は、自分たちで死刑の判決を出す事が許されていなかったそうで、イエス様に罪を認めなかったピラトが心ならずもイエス様に死刑の判決を下すことになる。こうしてピラトはイエス様の死刑が歴史上の出来事としてあったことの証人として神様に用いられている。信仰告白に「ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け」とあるように。 裁判というと、私が高校生の頃CS教師であった横山晃一郎先生(良樹牧師の父)を思い出す。先生は大学で法律を教えてみえて、聖書に書かれていることがところによってまちまちであるのは、むしろ真実である証拠だと言われた。それは同じ出来事を見ても受け取り方はみな違うのが当然だからで、同じように書かれていたらそれはむしろ作り話だと思ってよいと言われたのだった。(久美江) |
|||
| ■安田 志峰 |
|||


 
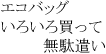
|
|||
|
トップページへ | |||
|
|
|||