| 2008年12月号 | ←前へ 次へ→ | ||
 |
|||
| 主はアブラムに言われた。「あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、わたしが示す地に行きなさい。」 | |||
| 創世記12章1節(新共同訳) | |||
| 今月からしばらくアブラハムが登場します。上の聖句にあるとおり最初はアブラムという名前でした。 アブラハムは、聖書を一生懸命読む人たちが「信仰の父」と呼ぶようになった人物です。今回はアブラハムの第1回目として、この「信仰の父」ということについて述べたいと思います。 中学の音楽の時間に「音楽の父」=バッハ、と習いました。試験問題として出れば、バッハのことを何も知らなくても、「音楽の父」=バッハで丸をもらえました。その当時は音楽も高校の試験科目に入っていましたから、点数を貰うための知識が必要でした。バッハは音楽の父でも何でもよいのです。ただそのように知っていると世間がそれを丸と認めてくれて、合格にもなるのでした。 それに対して、アブラハムを「信仰の父」と呼ぶ時、単なる知識としてそのように呼ぶのは、つまらないことです。この私に信仰についての信頼や示唆を与える何かがあってでないと「信仰の父」の場合、どこからも丸はきません。私に神様を思うことが力であることを示し、語りかけるところがあるので「信仰の父」です。しかも「父」ですから、導きを与えてくれる人は多くいても、その基のところにいる人物です。私自身が「信仰の父」と呼びたくなる、そういう存在だといったらよいでしょうか。 では、アブラハムの何を受け止めて信仰の先輩方は「父」と呼んだのでしょうか。それは “神様がいて私がいる”という一点でしょう。頭で分かるだけでは足りません。実際の足跡にその受け止めがあるのです。現実の人間の世界では、この生きざまは困難も生じます。「父なる神」の父ではありませんから、彼は、窮地に陥った時妻サラを妹だと偽って言ったりしますし、自分の知恵も経験も役立て、私たちの実の父親と同じような様子も見られるのです。しかしその者が神様がいて私がいるという道を進みます。 アブラハムに親しさを覚えて、私達も彼を「信仰の父」と呼んで、神様がいて私がいる人生を歩みたいです。 |
|||
 |
|||
| ■深津 玲実 | |||
 「放蕩息子の譬え」 「放蕩息子の譬え」ある人に息子が二人いた。 弟の方が、父親から、財産のうち自分の分け前を貰い、旅立ち、放蕩の限りを尽くしてそれを使い果たしてしまった。 その頃、飢饉が起こって、弟は、豚のたべるいなご豆ででも腹を満たしたくなった。 弟は我に返って言った。『ここを立ち、父のところに行って言おう。「お父さん、わたしは天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください」と。』 弟が父親のもとに行った時、まだ遠く離れていたのに、父親は息子をみつけて、憐れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。 「一日一章」より抜粋 放蕩息子は「罪を犯しました」と言った。 考えてみると、罪を犯しましたといっても、物を盗んだわけでも、不義理をしたわけでもない。ただ父からもらったという状況のもとで放蕩に使ったから罪なのであって、自分が稼いだ金を使ったのなら罪ではない。 私たちが罪について話すと、私は何もしていないと言う人があるが、それはキリスト教で言う罪とは違う。キリスト教の罪は、一人子をたまうほどに私たちすべての者を愛してくださったという状況のもとで、それほどの愛を受けている私たちが、その神に無関心でいること自体が私たちの罪というのである。 罪には、なしたる罪と、なさざる罪とがある。私たちはそのなさざる罪を、道徳とか理想などと考えやすいが、それはなしたる罪と同じ重さであって、神からは同じようにとがめられる。なぜなら私たちが神から愛されているという状況があるからである。 |
|||
| ■安田 志峰 |
|||
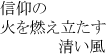



|
|||



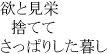

|
|||
|
トップページへ | |||
|
|
|||